獅子の生け捕りを演じる神楽 「和唐内」
 |
 本庄菅野地区にある上山神社では、毎年、春の例祭で神楽が奉納されます。 本庄菅野地区にある上山神社では、毎年、春の例祭で神楽が奉納されます。
菅野に伝わる神楽は、約350年ほど前に尾張から伝わったと云われています。
丹後の多くの神楽が出雲から伝わったのに対し、菅野の神楽は他地域とは明らかに違いを感じます。
伝わる神楽は12曲で、1、岡崎、2、神楽、3、剣の舞、4、花の舞、5、おそめの舞、6、玉の舞、7、天狗の舞、8、法螺の舞、9、両剣、10、不動の舞、11、大神女郎の舞、12、和唐内です。
昭和40年代に一時期継承者不足から中断もあったようですが、地域の皆さんの努力で見事復活して現在に至っているそうです
|
 |
 |
|
|

「和唐内」
獅子の生け捕りを演じる和唐内(わとうない)は、迫力のある立ち回りと衣装の早変わりが見もので、京都府の無形民俗文化財に指定されています。
|

|
|
|

「おそめの舞」
右手に扇子、左手に菅笠を持って踊る神楽は、迫力ある「和唐内」とは対照的に、女性のしぐさを表わした神楽の踊りで、とても印象的です。
|

|
|

「天狗の舞」
天狗は子供が演じており、ピョンピョン身軽に飛び跳ねます。
|

|
|
 「おかめ女郎」 「おかめ女郎」
大きな女役と小さな男役のしぐさがとてもユーモラスです。
「ひょっとこ」が「おかめ」を口説くストーリーらしく、踊りの合間に「そろそろ床入りしょうではないかいの~」などの掛け声が入るのも面白いです。
|

|
|
|
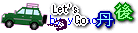 |
|
|